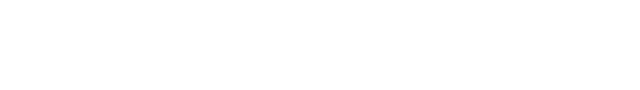第17回:国内初承認! 慢性腎臓病の新薬とは?
8月7日日経電子版より抜粋
もうだいぶ前の話になりますが、8月初旬にこのような記事が新聞に掲載されていました。
小さな記事ではありますが、腎臓病患者さんにとっては期待が持てるような内容です。
これまで私も腎臓専門外来をやってきましたが、「腎臓の特効薬というものはありません。」という言葉をお伝えし、落胆される患者さんをたくさんみてきました。
もし”特効薬”というものがあれば、多くの腎臓病患者さんにとってどれほど素晴らしいことかは、つくづく感じています。
では、今回承認されたこの新薬、”特効薬”になり得るものなのでしょうか?
うわさの新薬とは?
まず皆さんの期待を裏切るようなことを言ってしまうかもしれませんが、この薬、新薬ではありません。
フォシーガ®(ダパグリフロジン)という名前で糖尿病治療薬として2014年に発売され、糖尿病の方にはすでに使われている薬です。
このフォシーガ®は、SGLT2阻害薬(”エス・ジー・エル・ティー・ツーそがいやく”と呼びます)という種類の糖尿病治療薬です。
日本では同じ仲間のくすりが他にも6種類ほど発売されており、糖尿病の治療薬としては広く使われるようになっています。
ですから、厳密にいうと”新薬”ではないのです。
しかし、これまでは”糖尿病”の治療薬としてしか使えませんでした。
今回、「”慢性腎臓病”という病気に対して使えるよになった」という意味では一応、”新薬”になります。
そこで、この新しい慢性腎臓病治療薬がどのようなものか、一般の方でもわかるようかみくだいてご紹介したいと思います。
この治療薬は、どのように腎臓に作用するの?
糖尿病になると、ご存知の通り高血糖(血糖値が高い)の状態が続きます。
つまり血液中の糖の濃度が高いということです。
この高血糖状態が続くと、腎臓や神経、血管など様々な部分に悪い影響を及ぼすので、糖尿病は厄介です。
糖尿病の治療薬は数多くありますが、どれも色々な手段を使ってこの血糖値を下げようとしています。
中でもこのSGLT2阻害薬は、腎臓にはたらくことで血糖値を下げる特徴があります。
どのようにして腎臓にはたらくのかというと、「腎臓からたくさんの糖分を排泄させるように作用する」のです。
そうすると、体の中の糖分が減る(=血糖値が下がる)というわけです。
実はこの薬、発売当初から「腎臓を守る作用があるのではないか?」ということは、学会など盛んに議論されていました。
次にそれはなぜかをご説明します。
この治療薬は、なぜ腎臓病に効くの?
腎臓は血液の不純物を”ろ過”して尿をつくるはたらきをしています。
日本腎臓学会 「腎不全 治療選択とその実際」より改編
尿として膀胱(ぼうこう)に向かって出ていく前に、腎臓内の”尿細管(にょうさいかん)”と呼ばれる場所で、体に必要なものが残っていないかを再チェックしています(図)。
そしてやっぱりからだに必要だと思えば、この尿細管でもう一度回収(再吸収といいます)して、体の中に戻すことをします(図)。
高血糖の血液が腎臓でろ過されると、ろ過された後の尿にも糖分がたくさん含まれています。
人間を含む動物にとって、糖分というのはエネルギー源ですから、元々はとても大切なものです。
そこで、私たちには本能的に「糖分は大事なものだからなるべく捨てないようにしよう」という機能が備わっています。
すると、たくさん糖分が含まれた尿の元(原尿)が尿細管にやってくると、尿細管はそのたくさん糖分を目一杯吸収しようと頑張ってしまうです。
この頑張り過ぎの腎臓は、時間がたつと徐々にガス欠のように疲弊して腎臓が悪くなっていくのです。
ここでSGLT2阻害薬の出番となります。
先ほど書いたSGLT2阻害薬の「腎臓からたくさんの糖分を排泄させる」という作用、実は尿細管での糖分の回収(再吸収)を抑えているのです。
SGLT2阻害薬によって、無理やり糖分を尿に排泄させるようにすれば、腎臓は糖分を体に残そうと頑張り過ぎる必要はなくなります。
そうすれば、腎臓も通常運転することができるため疲弊せずに済むというわけです。
以上が簡単(!?)にまとめた、SGLT2阻害薬の腎臓への作用です。
では次に新薬として承認に至った研究をご紹介します。
腎臓治療の新薬として承認されるに至った根拠となる研究
この研究の名前は、DAPA-CKD(ダパ・シーケーディー)と呼ばれています。
この薬を投与した群と、偽薬(プラセボ)を投与した群とを比較して、「腎臓機能の悪化※1」に差があったかを約2年半にわたって見ています。
※1:この研究での「腎臓機能の悪化」とは、腎機能が50%以上低下、末期腎不全(透析や移植が必要なレベル)になる、腎臓や心臓などの問題で死亡するのいずれかを指しています
結果を簡単にまとめると以下のようになります。
・「糖尿病がある」慢性腎臓病患者さんの場合、この薬を飲まなかった人は、飲んだ人に比べて、約1.56倍「腎臓機能の悪化」が起こりやすかった
・「糖尿病がない」慢性腎臓病患者さんの場合、この薬を飲まなかった人は、飲んだ人に比べて、約2倍「腎臓機能の悪化」が起こりやすかった
N Engl J Med 2020; 383:1436-1446より引用・一部改変
また、慢性腎臓病があると、どうしても長期間かけて少しずつ腎臓機能は低下してきてしまうのですが、図のように薬を投与した群では、偽薬を投与した群と比べると、長期的には腎臓機能が下がりにくかったということです。
たしかに、この結果をみると、この薬は腎臓の機能を守る効果がありそうです。
ただし、ここで一つ注意点があります。
それは、この薬によって「腎臓機能が悪くなりにくくなる」のですが、「腎臓機能が良くなる(回復する)わけではない」ことです。
つまりこの薬も、悪くなった腎臓を元に戻すほどの”特効薬”ではないということです。
まとめ
先にもお書きした通り、SGLT2阻害薬の腎臓を守る効果は、以前より知られていました。
そして、腎臓の機能を回復させる力があるわけではないことも知られていました。
ですから、私たち腎臓内科医からすると、”特効薬”とまでは言い難いのが事実です。
しかし、これまで糖尿病の患者さんにしか使えない薬だったのが、慢性腎臓病の方に使えるようになったのは、大きな進歩です。
一方、高度な腎機能障害(eGFRが25ml/min/1.73m2未満)に対しては、制約があります。
※2:eGFR(イー・ジーエフアール)とは、腎臓機能をあらわす指標です。この値が25(ml/min/1.73m2)以下のなると、高度な腎機能低下と呼ばれます。
8月末に発表された新しい薬剤添付文書にも、eGFRが25(ml/min/1.73m2)未満の患者さんに対しては、「投与するかどうか慎重に判断すること」と、そして末期腎不全と呼ばれる患者さんは「適応から除く」と記載されています。
なぜなら、「尿から糖と一緒にナトリウム(塩分の一部)も排泄されるため、尿量が増えることから、脱水症を起こす危険性がある」のです。
実際、先ほどご紹介した研究でも、eGFRが25-75(ml/min/1.73m2)の患者さんを対象に行っています。
つまり、高度な腎機能障害(eGFRが25ml/min/1.73m2未満)の患者さんへの効果は検討されておらず、その効果は”未知数”というわけです。
腎臓病は、「悪くなっても症状が出にくく、末期になってから判明することが多い」病気であり、eGFRが25(ml/min/1.73m2)以下になってから、専門外来を受診される患者さんも少なくありません。
そのため、私たち腎臓内科医にとっては、「高度の腎機能障害になった患者さんの腎臓機能をいかに維持できるか」、「透析にさせないか」も、重要となります。
そういった意味では、「高度の腎機能障害の患者さんでも安全で、腎臓を守る効果がある」という証拠が揃えばいいのですが…
今後に期待したいところです。
いずれにしても、腎臓を守る手段が増えたのはとても喜ばしいことですね。
(追記)
9月に国際腎臓学会誌より、別な研究結果が発表されました。
それによると、このフォシーガ®(ダパグリフロジン)内服によって、慢性腎臓病患者さんの急激な腎機能悪化※(急性腎障害 Acute kidney Injury)の危険性が0.68倍に下がるという結果でした。
※ SGLT-2阻害薬は、発売当初は急激な腎機能悪化を起こす危険性が言われていました