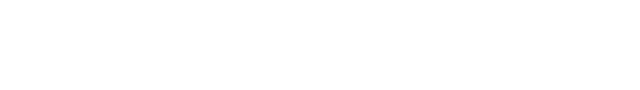水分制限のコツ:我慢だけに頼らない工夫とは
人工透析まめ知識、今回は多くの透析患者さんが悩む「水分制限」の話題です。
人工透析を受けていると、よく言われるのが「水分を控えてください」というアドバイス。
でも、「のどが渇いて仕方ない!」「夏は特につらい!」という声もたくさんあります。
ただただ我慢するだけでは長続きしません。
今回は、無理せず続けられる「水分制限のコツ」について腎臓・透析専門医がお話しします。
1.なぜ水分制限が必要なの?
人工透析では、体に溜まった余分な水分を取り除きます(除水と呼ばれます)が、
一度にたくさんの水分を除去すると、体に大きな負担がかかります。
特に次のようなリスクがあります:
血圧が下がりすぎて気分が悪くなる(低血圧)
筋肉がつって痛くなる(こむら返り)
透析が終わったあとも疲労感が抜けない
だからこそ、透析と透析の間にたまりすぎる水分(体重増加)を抑えることが大切です。
一般的には、透析間の体重増加5%未満(ドライウェイト60kgの人で3kg未)が目安とされています。
2.「水分」は飲み物だけじゃない?
意外と見落としがちなのが、「食べ物の中に含まれる水分」。
たとえば:
・お味噌汁やスープ類
・スイカ、みかん、梨などの果物
・アイスクリームやゼリー
これらもすべて「水分」としてカウントされます。
のどが渇いていないのに、こうした水分を無意識にとっていることもあるので注意しましょう。
3.我慢だけじゃない!5つの工夫
水分制限=つらい我慢、ではありません。ちょっとした工夫で、かなり楽になります。
(1)塩分を控える
味の濃い(塩分が多い)食事は、のどの渇きにつながります。
のどが渇けばその分、水分摂取も増えてしまいます。
減塩を意識するだけで、自然と水分のとりすぎを防げるようになります。
(2)飲み物の種類を見直す
一気に飲むとすぐに終わってしまいますが、たとえばレモン水や麦茶など、味がついているけど塩分やカフェインの少ない飲み物を少しずつ口に含むと、満足感が高まります。
(3)氷をなめる
冷たさが口の中に長く残るので、少量でも満足感があります。
家庭で製氷皿を使って小さな氷キューブを作るのがおすすめです。
(4)食事の温度も工夫
温かい汁物は蒸発も早く、つい量を飲みがち。
冷たいおかず中心にするとスープ類の摂取量も抑えられます。
(5)口の中を潤す工夫をする
透析患者さんは、健常人と比べて、口の中が乾燥傾向にあります。
「のどが渇く」のではなく「口が乾く」ことで水分を摂っていることはありませんか?
そんなとき、次のような対策が有効です:
-
ノンシュガーガムや飴(※糖分の摂りすぎに注意)
-
うがいや口をすすぐだけでも効果あり
-
ハブラシで舌を清潔に保つと口の粘つきが減ります
4.夏の用心!? 冬の油断!?
「夏は汗をかく分、水分が必要なのでは?」と感じるかもしれませんが、透析患者さんの場合、食事や水分を通常通り摂っていれば、脱水になることはマレです。
実際、たくさん動いたり、サウナに入ったりしても、透析間で体重が増えている(水分が溜まっている)ことが多いものです。
ただ、透析患者さんの場合、健常人よりも汗の量は少ないので、発汗による体温の冷却作用(体温調節作用)が落ちています。
そのため、「熱中症になってしまうリスクは高い」といえます。
夏は「脱水予防」としてたくさん水分を摂取することではなく、「熱中症予防」として涼しい部屋で過ごすことが大切です。
一方、冬は空気が乾燥しているうえに、のどの渇きを感じにくいため、逆に水分を多くとってしまうケースもあります。
そこで「体重で管理」することが一番の目安になります。
ご自宅でも体重の増え方を観察して、自分のペースを見つけましょう。
5.医療スタッフと一緒に「自分流の工夫」を見つけよう
水分制限の方法は、「正解がひとつ」ではありません。
生活スタイルや好みによって、合う方法・合わない方法があります。
自己流で悩まず、看護師さんや栄養士さん、医師に気軽に相談してください。
「水分を控えるのがつらい」と感じたときが「やり方をもう一度工夫するタイミング」なのです。
6.まとめ
水分制限は、人工透析を続けるうえでとても大切なポイント。
でも、「ガマン」「禁止」だけでは続きません。
日々の小さな工夫やコツを積み重ねながら、自分に合った「快適な制限のしかた」を見つけていきましょう。
当院では、みなさんの透析ライフが少しでも快適になるようサポートしていきます。