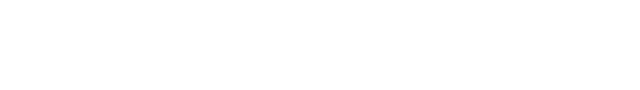第49回:紅麹による腎障害とは?
小林製薬が販売した「紅麹」成分配合のサプリメントを摂取した人からの腎障害を含む健康被害が相次いで報告され、大きなニュースになっています。
NHKニュースより引用
このサプリ、私も知りませんでしたが、「コレステロールを下げる」という効能を謳ったものだそうです。
さらにこの紅麹を使った食品が多数あり、自主回収が相次いでいます。
この紅麹と関連している可能性がある”腎障害”がどのような障害だったかまだ明らかではありませんが、
食品やカビなどが関連する急性の腎障害※だとすれば、
「急性尿細管壊死(きゅうせい にょうさいかん えし)」もしくは、
「急性尿細管間質性腎炎(きゅうせい にょうさいかん かんしつせい じんえん)」などが想定されます。
そこで腎臓専門医の立場から、尿細管の働きと「急性尿細管壊死」、「急性尿細管間質性腎炎」についてご説明したいと思います。
※ コラム「急性腎障害とは?」もご参考ください
”尿細管”とは?
腎臓は血液の老廃物を排泄すために「尿を作る」臓器です。
2023年版 腎不全 治療選択とその実際より
「尿を作る」過程において、”ろ過”と”再吸収”と呼ばれる2つの重要な段階があります。
そして、”ろ過”の役割をするのが 「糸球体(しきゅうたい)」、
”再吸収”の役割をするのが 「尿細管(にょうさいかん)」です。
まずは、”ろ過”から
”ろ過”とは、コーヒーで使うろ紙のような役割です。
血液は腎臓に送られて来ると、糸球体を通過して、”ろ過”され、老廃物と大事な栄養素に分別されるのです。
ここで、ハンドドリップコーヒーを想像してみましょう。
腎臓における”ろ過”のしくみ
お湯が血液、コーヒーが尿(原尿)、そして、ろ紙が糸球体というイメージです。
お湯(血液)を注ぐと、ろ紙(糸球体)を通過して、コーヒー豆はポットに落ちることなく、
液体のコーヒー(尿)だけが、ポットに溜まります。
血液には身体に大事な栄養素(赤血球やたんぱく質)がたくさん含まれており、
コーヒー豆のようにろ紙内(体内)にその栄養素を残す必要があります。
その、ろ紙の役割を「糸球体」がしているのです。
次に”再吸収”
ろ過されて出てきた原尿は、まだまだたくさんの栄養素やミネラルなどが含まれています。
さらに、原尿は1日150リットルも作られるので、そのまま尿として出ていってしまっては、体中の水分がなくなってしまいます。
そこで、この原尿に含まれる身体にとって必要な水分や栄養素(今度はアミノ酸やブドウ糖など)、ミネラル(塩分やカリウム、マグネシウムなど)を
「もう一度体内に吸収する=”再吸収”」してくれる場所が「尿細管」です。
この”再吸収”によって、体内の水分量を一定に保ったり、
ミネラルのバランスを調整したり、身体を弱アルカリ性の状態に保つことができるのです。
急性尿細管壊死とは?
この”再吸収”を行う場所が、何らかの理由で急激に壊されてしまうのが、「急性尿細管壊死」です。
原因は様々ですが、薬物(鎮痛剤や抗がん剤、抗生物質、造影剤、漢方薬など)による中毒性の副作用や、
重篤な細菌感染症などで起こることが多く見受けられます。
そのほか、「夏の脱水症で腎臓が悪くなる」と聞いたことがあるかもしれませんが、その状態が長く続くことでも起こる場合があります。
急性尿細管壊死の症状
先ほどご説明した通り、尿細管でのさまざまな”再吸収”の障害が起こるので多尿になり得るのですが、
急性尿細管壊死のような急激な障害の場合には、壊死した細胞などが尿細管に目づまりを起こして尿が出なくなり、
”むくみ”として自覚することがあります。
そして、尿が出ない状態が長く続くと、人工透析が必要になることもあります。
ただ、「腎機能が少し悪くなった」段階では、”夜間の頻尿”だったり、”尿の泡立ち”や”血尿”などで自覚する場合もあります。
その他、ミネラルバランスの異常(電解質異常)や、時間が経つと「尿毒症のような症状」も出現します。
急性尿細管間質性腎炎とは?
「間質(かんしつ)」とは、上記の「糸球体」や「尿細管」の周りをとりまく組織をのことをいいます。
この部分に炎症が起こることを「間質性腎炎」と呼び、特に尿細管周囲の「間質」に起こる
急激な炎症を「急性尿細管間質性腎炎」といいます。
原因としてはこれも様々ですが、薬物(鎮痛剤や抗がん剤、抗生物質、漢方薬など)のアレルギー反応で起こることが多いとされています。
急性尿細管間質性腎炎の症状
間質と呼ばれる部位にアレルギー反応と炎症が起こるため、発熱や発疹のほか、
腎臓がある場所(両側背部)の痛みを伴うことがあります。
また尿細管に障害が起こると、多尿のほか、ミネラルバランスの異常(電解質異常)が起こります。
そのほか急性尿細管壊死のときと同様に、
発症初期は”夜間の頻尿”、”尿の泡立ち”や”血尿”などで自覚する場合もあります。
さらに障害の程度が強くなると、尿が出なくなることもあり、”むくみ”として自覚するようになります。
そして、尿が出ない状態が長く続くと、人工透析が必要になることもあります。
尿細管・腎臓の障害はどうやってわかるの?
もちろん上記したような何らかの症状が出現すれば疑うことになりますが、
はっきりと尿細管間質障害や腎障害の有無を確認するには、血液検査と尿検査が基本となります。
血液検査では、腎臓の機能やミネラルバランスが確認できます。
また尿検査では、尿中に含まれる「電解質」や「たんぱく質」のほか、「尿細管障害のときに増えるマーカー」などが確認できます。
さらに状態をくわしく調べるために、”腎生検”という「腎組織の状態を直接顕微鏡で確認する」検査が必要になることがあります。
結局、紅麹による腎障害とは?
先ほど書いた通り、「急性尿細管壊死」もしくは、「急性尿細管間質性腎炎」だった可能性※があります。
※ あくまでも個人的な見解で、今回起きた腎障害の原因はまだ明らかではありません
(今回の紅麹製品には含まれていなかったそうですが)紅麹菌の中には「シトリニン」というカビ毒をつくって、腎臓の障害を引き起こすものもあるらしいです。
そして、この「シトリン」というカビ毒も尿細管の超微細構造を損傷することで、腎障害を起こすようです。
今回の一件も「サプリに混入した何らかの物質」が中毒性の作用を起こし、急激に腎臓が働くなった可能性があります。
その場合には、急性尿細管壊死に至ったと考えられます。
一方で、「サプリに混入した何らかの物質」によるアレルギー反応で腎障害が起こったとすれば、急性尿細管間質性腎炎だった可能性が考えられます。
その場合、炎症やアレルギーに関連する症状(発熱や発疹、背部痛など)を伴っていたのではないかと考えられます。
また、アレルギー反応で起こることが多いため、服用始めてから比較的短期間のうちに発症した可能性も考えられます。
まとめ
今回の一件は思った以上に様々な食品にまで波及しており、大きな話題となっています。
紅麹サプリを内服していた方、関連食品を摂取していた方は非常に不安かと思います。
気になる症状があれば、かかりつけ医やお近くの腎臓専門医に一度ご相談してみるのが良いでしょう。
※ 今回は、尿細管とその障害についてを中心にご紹介しましたが、紅麹の腎障害の原因はまだ明らかになってないことにご留意下さい。
「急性腎障害」についてのコラムは ⇒こちら