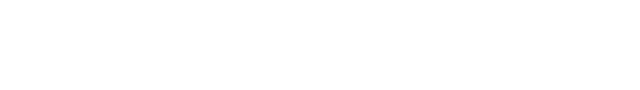第6回:アストラゼネカワクチンは大丈夫? ~うわさの”血栓症”とは~
ヨーロッパ諸国を中心に投与されてきたアストラゼネカ製のコロナワクチンですが、いよいよ日本でも大規模接種会場を中心に投与が行われるようになってきました。
アストラゼネカ製ワクチンというと、多くの方々が気にされるであろうこととして、”血栓症”という副反応があるかと思います。
そこで、アストラゼネカ製ワクチンについて少し見ていきたいと思います。
アストラゼネカ製ワクチンは、イギリスの大手製薬メーカーアストラゼネカ社とオックスフォード大学が共同で開発したものです。このワクチン、ファイザー製やモデルナ製のものと、そもそもが大きく異なります。
ファイザー製やモデルナ製ワクチンは、メッセンジャーRNAワクチンという種類です。これは、メッセンジャーRNAという物質を直接投与します。
メッセンジャーRNAはからだの中で、スパイクたんぱく質という物質を作るよう細胞に働きかけてくれます。
人のからだは、スパイクたんぱく質を確認すると抗体を作るようにできているので、抗体が生成されてウイルスに対する予防効果を発揮します。
一方で、アストラゼネカ製のワクチンは、ウイルスベクターワクチンという種類です。
先ほど出てきたスパイクたんぱく質の”設計図”となる遺伝子を、無害なチンパンジーのアデノウイルスに組み込み、そのウイルスごと投与します。
すると、人の細胞は無害なウイルスであっても、ウイルスに感染したと勘違いをして、スパイクたんぱく質を作り、それを受けてやはり抗体が作られ、同様に予防効果を発揮するようになるのです。
どちらのワクチンもスパイクたんぱく質を作るきっかけになるものを投与するわけですが、その働きかけ方が異なるということです。
ただ、どちらのワクチンが効果が高いのか、安全なのかははっきりとわかってないのが現状です。
では、このコラムを読んでくださっている皆さまが一番気にされているであろう、アストラゼネカ製ワクチンの”血栓症”に関して現時点でわかっていることをご紹介します。
・どのような人に多く発生しますか?
39の発生事例をまとめた海外の文献(N Engl J Med 2021; 384:2254-2256)によると、比較的若い(50歳未満)、女性に多かったそうです。
しかし、先日発表された294症例(疑い例も含む)をまとめた研究によると、女性の割合が54%と若干は多かったものの、性別に大きな差はなかったとのことでした。
年齢については、平均48歳(18-79歳の幅)であり、50歳未満の発生率(5万分の1)は、50歳以上の発生率(10万分の1)と比べると2倍程度の可能性があるそうです。
しかし、この研究だけでは、データが不足しており、年代別の発生率まではわからなかったとのことです。
結局、今わかっていることとしては、以下のことのようです。
① 女性の方がやや多い可能性はあるがそれほどの性差はない
② 50歳未満は注意を要する
しかし、”血栓症”の報告は、今年3月になって初めて欧州で明らかになってきました。
これは、若い世代にワクチンが供給されてきた時期と重なっており、それ以前に投与された高齢者については調査されていなかったのです。
そのため、高齢者の”血栓症”の発生が見逃されていた可能性もあり、本当に若い世代に多いのかも未だ明確でないようです。
・どのタイミングで発生しますか?
上でご紹介した論文の全例において、1回目の投与後に発症しています。時期は、ワクチン投与後5-48日後(平均14日後)くらいが多いようです。
・”血栓症”はからだのどこに起こるのでしょうか?
血栓症を発症した方の約半数が脳静脈(洞)だったようです。
また、脳静脈(洞)血栓症を発症した人の36%は脳出血を合併していたとのことです。
そのほか、いわゆるエコノミークラス症候群と同じような下肢静脈・肺動脈の血栓症が37%、お腹の臓器に関わる静脈血栓症が19%程だったようです。
・”血栓症”の死亡率が高いと聞きましたが本当ですか?
最近、メディアでもこのことについては度々報道されています。
上でご紹介した論文によると、血栓症を発症した人の22%が亡くなったそうです。
特に、脳静脈(洞)血栓症が発生すると、死亡率は2.7倍になるとのことです。
・”血栓症”の治療法はあるのでしょうか?
現段階では、確定された治療はないようです。
しかし、免疫グロブリンやステロイドの他、抗凝固薬と呼ばれる血栓を溶かす薬などが投与されています。
また、”血漿交換”と呼ばれる私たち透析専門医の分野である治療法を使用した場合、重篤な血栓症が発生した場合も90%の生存率を示したとのことです。
・ファイザー製、モデルナ製のワクチンでも、血栓症は起きるのでしょうか?
欧州医薬品審査庁(EMEA:The European Medicines Agency)のレポートによると、アストラゼネカ製を投与した3400 万人にのうち223例、ファイザー製を投与した5400万人のうち35例、モデルナ製を投与した400万人のうち5例の血栓症を疑う例が発生しているそうです。
但し、このデータは厳密な検証が行われていないため、”可能性がある”というだけで、ワクチンとの関連性が明らかなわけではありません※。
この確率を10万人あたりの頻度にすると、以下となります。
| アストラゼネカ製 | 0.66人 |
| ファイザー製 | 0.065人※ |
| モデルナ製 | 0.13人※ |
これを見ると、どのワクチン投与でも、(その関連性は不明ながら)血栓症は起こり得ますが、アストラゼネカ製の頻度が多いように見えます。
しかし、一般的(ワクチンを打ってない通常時)に脳静脈(洞)血栓症の発生率が10万人あたり0.22〜1.57例と推定されています。それと比べてみると、アストラゼネカ製であっても必ずしも多いわけではないことがわかります。
・まとめ
以上を読んでいただくと、アストラゼネカ製ワクチンによる”血栓症”について、「ようやく傾向はわかってきた段階であり、未だ不明な点が多い」のが事実です。
ですから、「だれも正しい助言ができない」というのが現実でしょう。
”血栓症”の発生率が10万人あたり1-2人前後を高いと考えるか、低いと考えるかは個人の問題になってしまいます。
ただ、全国の1日新規感染者数が2万人を超えた現在、(単純計算をしてしまいますと)感染する確率が10万人あたり16人前後であることも知っておく必要があります。
1日も早くワクチンを打ちたいと思いながらも、モヤモヤした不安感によって接種を迷っている方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
本コラムを読むことで、モヤモヤの解消にはならないかもしれませんが、正しい認識を持って接種をしていただければと思います。